様々な香りを持つハーブたち。料理に素敵な香りを添えてくれますね。
香りを科学する その1「ハーブの香りは料理で変わる?!」では、ハーブの香りが調理方法によってどんな風に変わってくるか、シソ科のハーブ・ローズマリーを例にして紹介しました。
今回は、顕微鏡で香りの素を探ってみましょう。
Qこれは何でしょう?
下のA、B、Cは、3種類のハーブのある部分を顕微鏡で見た画像です。
これらはいったい何でしょうか?
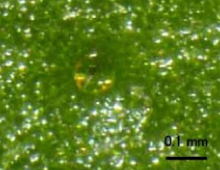 A-1
A-1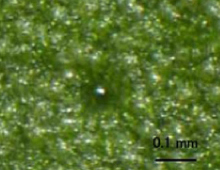 B-1
B-1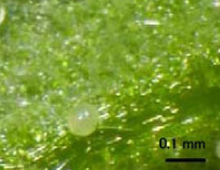 C-1
C-1
少し遠ざかってみましょう。
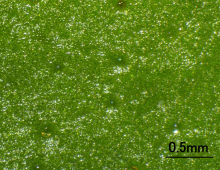 A-2
A-2
イタリア料理によく使われ、ジェノベーゼソースに欠かせないハーブです。
 B-2
B-2
すーっと清涼感のある香りで、ハーブティーやデザートによく使われているハーブです。
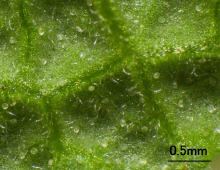 C-2
C-2
もこもこした葉の表面が特徴的な豚肉と相性抜群のハーブです。
正解は…
 Aスィートバジル
Aスィートバジル Bペパーミント
Bペパーミント Cセージ
Cセージ
いかがでしょう?
植物の画像をご覧いただくとおわかりですね?
3種類とも、シソ科のハーブで、これらの葉を顕微鏡で拡大したものです。
そして、A-1、B-1、C-1の画像の粒状の部分が、それぞれの特徴的な香りの成分をたくわえているところで、植物学的には「腺毛(せんもう)」(glandular trichome)と呼ばれる器官です。
この器官がつぶれると、香りが出てきます。
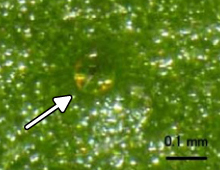 A-1 スィートバジルの腺毛
A-1 スィートバジルの腺毛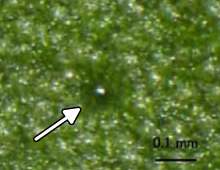 B-1 ペパーミントの腺毛
B-1 ペパーミントの腺毛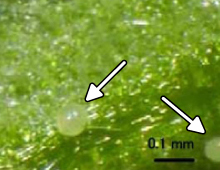 C-1 セージの腺毛
C-1 セージの腺毛
このように、シソ科のハーブでは腺毛に香りの成分がぎゅっと詰まっているのです。
香りがするのは葉だけ?
生い茂るハーブからふんわりと香りを感じて近づき、ハーブの葉を触った瞬間、急に強い香りを感じることはありませんか?
これは、ハーブに触れることで、腺毛がつぶれ、香りが放出されるからです。言ってみれば、香りの玉手箱を開けると、香りが飛び出してくる…というイメージです。
シソ科のハーブでは、腺毛が、葉や茎などあらゆる部分にあり、たとえばローズマリーの場合、葉だけでなく、茎も香りの玉手箱でいっぱいです。
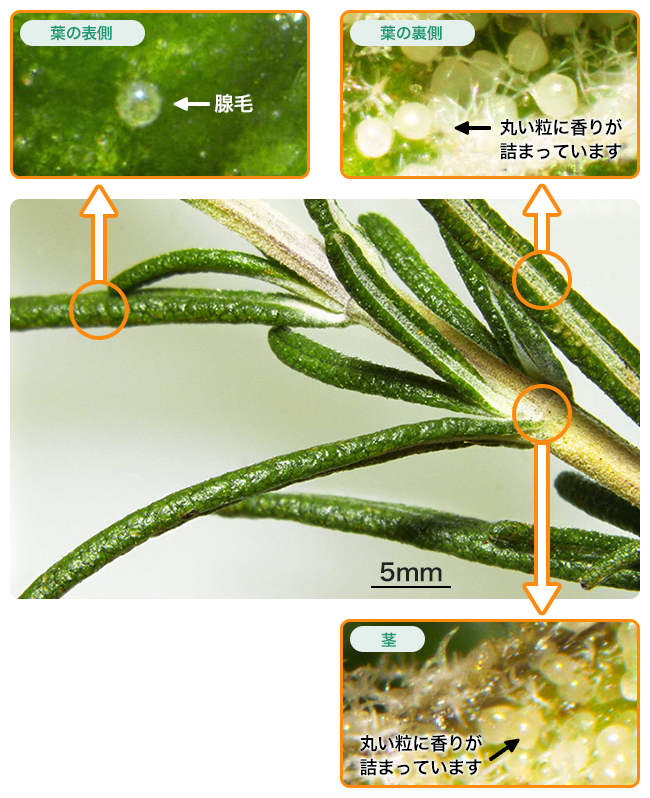
このように、ふだん見えないところに、香りの素が隠れています。
みなさんの香りを楽しむ幅が広がったでしょうか?
エスビー食品ではハーブの香りに関する様々な研究を進めています。
ローズマリーの腺毛に関する研究成果を第26回日本香辛料研究会で発表しました。
