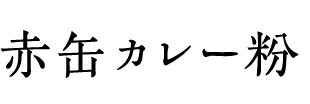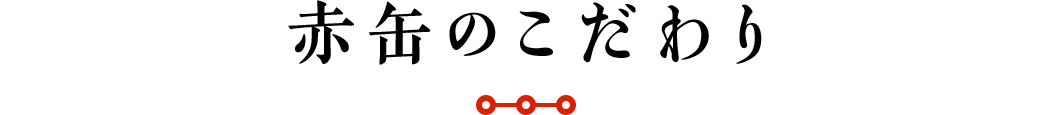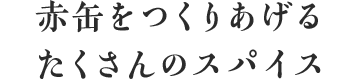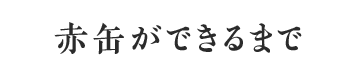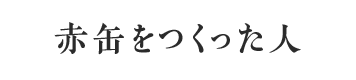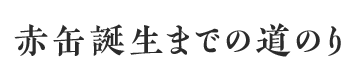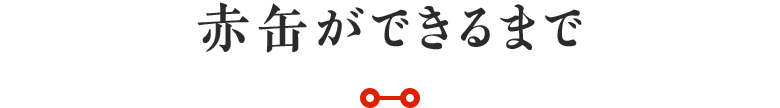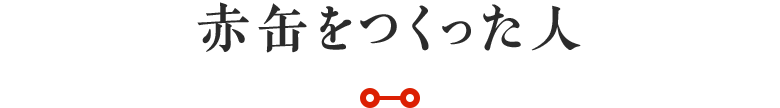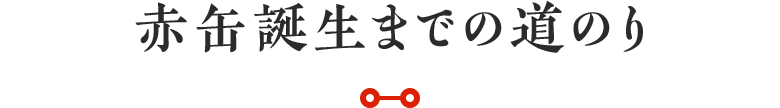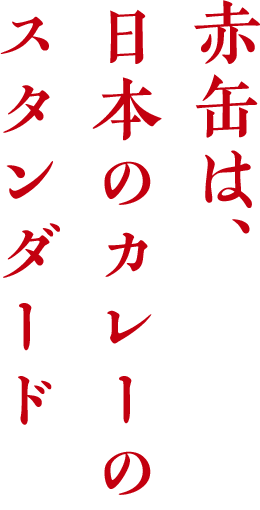
日本で初めて純国産のカレー粉が誕生したのは、
1923年(大正12年)のこと。
そして赤缶カレー粉は、
今でもその当時に確立された秘伝の製法をベースに製造され、
日本中のキッチンで愛され続けています。
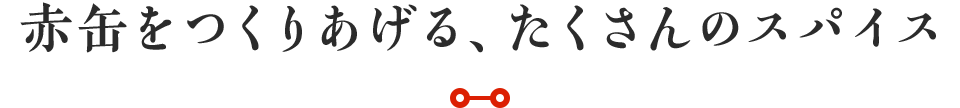
赤缶カレー粉にブレンドされている
30数種類のスパイスのうち、
代表的なものをいくつかご紹介します。
-

ターメリック
黄色の色づけに活躍するスパイス。独特のやや土臭いような香りは、加熱することで弱まり、料理の味に厚みを与えます。
-

コリアンダー
パクチーの種子を乾燥させたもの。甘く爽やかで、ほのかにスパイシーな香りは、味付けに深み、奥行きを加えます。
-

クミン
エスニックで強い芳香をもったスパイス。カレー粉やチリパウダーの原料に欠かせません。
-

フェネグリーク
種子にじっくり火を通すと苦みが弱まり、メープルシロップのような甘い風味が出てきます。深みのある本格的な味わいに。
-

こしょう
「スパイスの王様」とも呼ばれ、口内に広がる爽快な香りとピリリと刺すような刺激的な辛みがあります。
-

赤唐辛子
ヒリヒリするホットな辛みを持つスパイス。色、形、大きさ、辛みなどが違うさまざまな品種があり、約3千種にも及ぶといわれています。
-

ちんぴ
ウンシュウミカン(またはマンダリン)の皮を乾燥させたスパイス。ほのかに爽やかな柑橘系の香りをもっています。
赤缶1個1個に、
エスビー食品が受け継いできた技術とノウハウ、
そして私たち一人ひとりの”想い”が詰まっています。
-
製粉
スパイスやハーブを粉にする工程です。粉にするときの熱の発生と組織の破壊が最小限におさえられ、スパイスやハーブの香りを生かすことができる「スタンプミル」という機械にこだわっています。
-
計量・投入・混合
粉にしたスパイスやハーブをはかりで計量し、機械に投入して混ぜ合わせます。調合のバランスは、エスビー食品が昔からほとんど変えずに守ってきたものです。
-
焙煎・貯蔵・熟成
スパイスやハーブの中に残っている水分を飛ばして、焦げない程度に熱を加えてじっくり煎っていくと、カレー粉らしい香りが生まれます。
焙煎したカレー粉はタンクの中で寝かせて熟成させ、バラバラだったそれぞれのスパイスやハーブの香りをひとつにまとめます。 -
製品仕上げ
底があいた缶の中に空気を吹き付けてゴミが入らないようにしてからカレー粉を入れます。缶にフタ(底)をのせ、ふちを丸く巻き込んで、ぴったりと密封して仕上げます。
-
保管・出荷
すべての工程を終えてできあがった赤缶は、倉庫に保管された後、みなさんが住む町に運ばれ、店頭に並べられます。エスビー食品が受け継いできた様々な技術とノウハウ、そして私たち一人ひとりの”想い”が詰まっている赤缶が、みなさんの家庭に届きます。

エスビー食品 創業者
山崎峯次郎
1903年(明治36年)、埼玉県北葛飾郡金杉村に生まれる。17歳で上京し、ソース屋に勤務。この頃に初めて食べたカレーライスの味に深く感動した山崎は、自らの手でカレー粉の製造をすることを決意します。
当時は外国製のカレー粉が一般的で、その製法は全く知られていませんでした。
山崎は原料一つ一つを確かめながら調合を繰り返す日々を送り、その焙煎方法や焙煎する道具に至るまで、独自で開発を続けました。
そしてついに、日本で初めての純国産カレー粉の製造に成功。エスビー食品の前身「日賀志屋」を創業したのです。
-
1923年(大正12年)
日本初の純国産カレー粉誕生
業務用(1ポンド缶・1円10銭)にて純国産カレー粉の販売がスタートしました。

-
1930年(昭和5年)
ヒドリ印カレー粉 発売
初の家庭用カレー粉を発売。「ヒドリ印」は、社運や製品への願いを込めた「太陽」と「鳥(鳩)」がモチーフになっています。

-
1933年(昭和8年)
白缶カレー粉 発売
著名な料理家の推薦状を商品に添付することで、料理人たちへの売込みに成功。また、当時では珍しい景品キャンペーンなどによるカレー文化の啓蒙にも貢献しました。

-
1950年(昭和25年)
赤缶カレー粉 発売
戦時中〜終戦後の原料や物資不足を乗り越え、創業以来培ってきたノウハウの集大成として「赤缶カレー粉」が誕生しました。